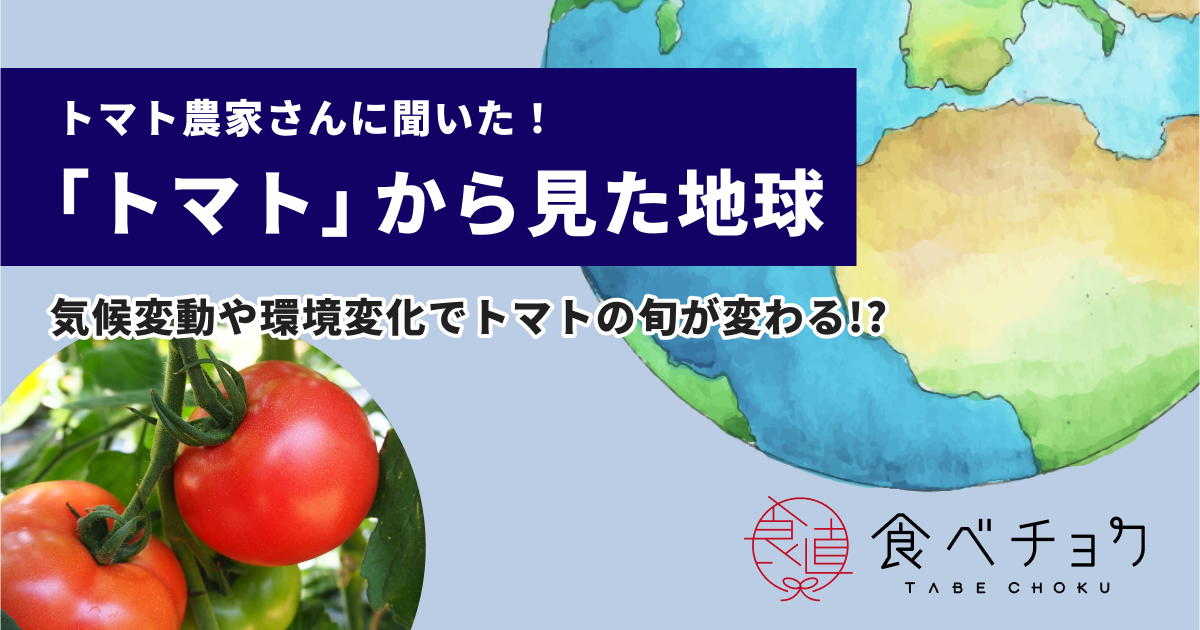
トマト農家さんに聞いた!<トマトからみた地球> 気候変動や環境変化でトマトの旬が変わる!?
食べチョクでは、2024年9月に鹿児島~北海道までトマトを生産する農家さん44軒に生育環境についてアンケートを実施しました。
栽培方法については8割方がハウス。浮き彫りになったのは、やはり気温上昇や異常気象による大きな影響でした。
中には「温暖化によりいずれトマトの生産ができなくなる」と大きな危機感を感じる農家さんもいらっしゃるほど。
トマト生産をめぐる現場で何が起きていて、どのような対策を講じているのか。農家さんの「いま」をまとめました。
トマトと気候変動の今
高温による着果率の低下や果実の品質の悪化
近年の猛暑は私たちの日常生活に大きな影響を及ぼしています。
それは農家さんも同様で、高温や強い日差しはトマトの生育に大きな弊害を生んでいます。
たとえば着果率の低下。通常は花が咲き、実がトマトへと成長するのですが、
花の段階で落ちてしまったり(花落ち)、実がならなかったりという異常事態が起きているそうです。
また、実がなっても色づきや味ののりが悪かったりと出荷に至らない実も増えています。
このままでは、トマトの出荷が全くない時期も出てきてしまうのではという危惧を抱いているの農家さんもおりました。

収穫時期の変化や収量の低下
トマトの旬は通常、初夏から夏の間で、5月下旬~8月が出荷量のピーク。
しかし近年、5~8月期の高温が影響し収穫時期が早まったり、後ろ倒しになったりと、気候に左右され安定しないのが現状です。
収穫量に関しても、暑さによる裂果(実が割れてしまうこと)や
グリーンバック(実の上が緑のままになること)、過熟が早くぶよぶよになったりと商品としての基準を満たせず、時期によっては収穫量が減ってしまっています。
これは生産者である農家さんにも大打撃ですが、消費者である私たちの食卓にも大きな波紋を広げていくのではないでしょうか。
暑さだけではない異常気象の影響
高温による数々の影響もさることながら、トマトの現場を襲う異常気象は他にもあります。
たとえば、季節外れの長雨による日照時間の低下は生育を遅らせてしまいますし、
梅雨の時期に雨が少なかった北海道でも降雨量は増え、栽培方法の見直しも必要になってきているそうです。
さらに各地で頻発するゲリラ豪雨や台風は、ハウスや農地そのものを破壊しかねない恐ろしい状況です。
自然と共存しつつ、持続的に農作物を作り続けるためにはこういった問題のひとつひとつと向き合っていかねばなりません。
トマトを守る農家さん

日差しや高温からトマトを守るために
今回アンケートを実施した農家さん44軒のうち38軒はハウスでの栽培です。
室内はやはり高温になるため、様々な対策を講じています。
遮光剤や遮熱剤の噴霧、遮光カーテンの使用、ミスト散布、
換気システムのアップデートなど試行錯誤を繰り返し、トマトの生育環境を守っていました。
また、土壌においても暑さに強い根を育成するためのサプリを灌注したり、
中にはバイオスティミュラントという新しい概念の農業資材(植物や土壌により良い生理状態をもたらす様々な物質や微生物)
を用いて対策を講じている農家さんもいました。
品種変更や定植時期の調整など農家さんの挑戦
根本的な対策として暑さに強く、生産性の高い品種に変更する農家さんもいました。
具体的には「千果」や「桃太郎」シリーズなど高温でも着果が安定し、玉が硬いため裂果も少ない品種。
もちろん味も折り紙付き。「千果」も「桃太郎」も糖度が高くうま味が豊富で、ほどよい酸味がバランスを保ちます。
今の日本の気候にあった品種を試すのも、今後トマトを安定的に作り続けていく上で大きな対策のひとつです。
また、定植時期に関しても、前倒しして夏の暑い時期に樹を成長させ、収穫のピークを9月に持っていく農家さんや
あえて初夏前にピークを持っていく農家さんなど、各々が試行錯誤を繰り返し、私たちの食卓にトマトを届けてくれています。

まず「人」ありき
ここまでトマトの生育に関する農家さんの現状と奮闘をお伝えしておりましたが、猛暑は当然ながら生産する「人」にも影響を及ぼしています。
ハウス内高温のため、早朝と夕方しか作業できないといった声や「正直、自分がいつ倒れてもおかしくない」といった不安の声も聞かれました。
あるいは、そもそもの人手不足で収穫時の人員が確保できず、せっかく実ができても出荷が遅れてしまうなどの事象も起きています。
様々な策を講じて、あるいは愛を注いでトマトを育てるのは、間違いなく「人」。
大前提として生産者さん自身の身を守ることが、トマトを守ることにつながることをこのアンケートを通じて再確認しました。
いま一度トマトと向き合って
地球のために、トマトのためにできること
気候変動や環境変化に多大な影響を受けている農家さんですが、
今回のアンケートで流通に関して「変化した点」について多かった解答は地球環境への配慮でした。
プラスティックパッケージをやめて、バイオマス素材配合のものにしたり、
包装そのものを簡易的なものに変えたりしていました。
そして、輸送時のつぶれを防ぐための緩衝材や梱包の工夫、出荷できない実はジュースなどに加工して販売するなど
余すことなく使用して、ロス(廃棄)を出さないことも大きな意義があります。
気候の弊害はあるものの、これからも自然と共生し、持続的にトマトを生産するための配慮も欠かせません。
これからも美味しいトマトとともに
夏の旬を彩る瑞々しいトマトが、太陽の季節から姿を消してしまうかもしれない。
お弁当に欠かせないミニトマトが、高級品になっているかもしれない。
今後さらに温暖化が進めば、このような事態も起きかねません。
たまーに、ふと、トマトの背景にこんなストーリーがあることに
思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。
そして、今あるトマトを無駄にせず美味しくいただくことが
私たちができる最善の対策だと思っています。
さて、今日はどのようにトマトを召し上がりますか。
最新のおすすめ記事

【国産完熟・産直プレミアム】 極上さくらんぼ「紅秀峰」や「佐藤錦」など勢揃い
“本当に美味しいさくらんぼ”を食べたいあなたへ今にも弾けそうな艶やかな1粒…肉厚な果肉が弾けた瞬間に口いっぱいに広がる濃厚な果汁…何個でも食べたくなる絶妙な甘みと酸味…その美味しさを存分に楽しみたいなら、採れたてを味わうのがポイント。凄腕の生産者さんが、最も美味しいその時を見極めて収穫した採れたての極上さくらんぼを、産地からご自宅に直接お届けします。生産者さんが厳選した極上の逸品をぜひご賞味ください。極上さくらんぼを探すこだわりの特選果実を、特別なあの方へ、自分へのご褒美に初夏の味覚といえ...
2025/05/20 公開

【食べチョク実食レポート|柑橘編】こんなに違う!?個性豊かな柑橘
ひとくちに「柑橘」と言っても、品種や生産地によって、多種多様な味わいが楽しめます。さっぱり爽やかなタイプから、濃厚ジューシー系、はたまた香り高い個性派まで。旬の柑橘を食べ比べてみると、それぞれの“らしさ”がぐっと感じられます。お気に入りのひとつを見つけるもよし、家族や友人と感想を言い合いながら味わうもよし。このページでは、そんな“味わう体験としての柑橘”を楽しむヒントをたっぷりご紹介します!柑橘を探す >今日の柑橘試食ラインナップ私たちが手にする柑橘のひとつひとつには、気候に向き合い...
2025/05/19 公開
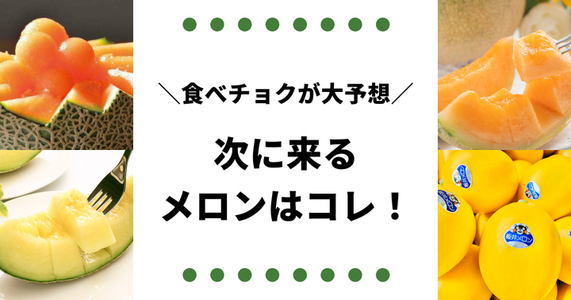
マスクメロンだけじゃない、次にくるメロンはこれだ!次のスター品種を大予想!
メロン界は、次のスターを待っている!ご褒美フルーツの代表格、メロン。日本では古くからウリの性格が強い東洋系メロンが庶民生活で親しまれていました。近代化以降、西洋からマスクメロンなどの西洋系メロンが一気に入ってきましたがかなり高価なもので、庶民層にはほとんど流通しませんでした。そんななか、1960年に「大衆メロン」の代表格であるプリンスメロンが開発され、それ以降メロンの品種は群雄割拠。後味さっぱりな青肉系・濃厚なコクが特徴の赤肉系・食べやすくなめらかな白肉系の3種類の味の違いを是非感じてほし...
2025/05/16 公開

“見た目じゃない、味で選ぶ魚”──未利用魚の魅力と、おいしい付き合い方
近年、魚の流通にも“かたち”や“基準”が求められるようになり、味に問題がなくても市場に出回らない「未利用魚」が目立つようになりました。サイズが不揃いだったり、見た目が個性的だったり、水揚げ量が少なかったりという理由で、出荷されずに破棄されてしまうことも珍しくありません。今回は、そんな未利用魚が生まれる背景と、いま注目される理由、そして“見た目ではなく、味で選ぶ”楽しさ、さらには家庭での活用方法までをご紹介します。【目次】 「未利用魚」って、どんな魚? “おいしくて、地球にもやさしい”...
2025/05/15 公開

夏に食べたい!「すもも・ワッサー・ネクタリン」の魅力と選び方
桃だけじゃない!“夏の主役果物”を見逃さないで毎年夏になると、スーパーや果物専門店で目にするのは“桃”が中心。でも実は、今こそ味わってほしいのが「すもも」「ワッサー」「ネクタリン」といった“通好み”の夏果物たちです。今回の記事では、食べチョクで手に入る上記3種の果物の違いや魅力、おすすめの食べ方をご紹介します。【目次】 爽やかで美味しい健康果実「すもも」の魅力とは? 桃とすもものハイブリッド「ワッサー」の美味しさとは? つるんとした見た目が特徴!「ネクタリン」は皮ごと食べられる夏の...
2025/05/15 公開

